3M悠々クラブ“ウォーキングの会”
第240回 池上本門寺を参拝して池上梅園で梅を愛でる報告書
2025年2月19日
池上本門寺は、東京都大田区池上にある日蓮宗の大本山。寺格は大本山、山号を長栄山、院号を大国院、寺号を本門寺とし、古くより池上本門寺と呼ばれてきました。また日蓮入滅の霊場として日蓮宗の十四霊蹟寺院のひとつとされ、七大本山のひとつにも挙げられています。
池上梅園は丘陵傾斜を利用した庭園で、四季折々の風情を楽しむことができる都内屈指の梅の名所です。2月から3月にかけて7万人ものお客様が来場されます。

2月18日、天気は良かったですがちょっと寒い中、東急池上線池上駅改札出口に13名が集合しました。

北口から少し北に歩くと本門寺通りと書かれた通りがありました。

そこを歩き、突き当たりを右折して広い道に出て、左折してしばらく歩くと池上本門寺への総門が現れました。そこをくぐると加藤清正が寄進した96段の石段が現れますので上がりました。石段を上がるのがつらい方は右側にある池上会館のエレベーターを利用しました。


石段を登ると仁王門が現れました。
1. 仁王門(三門)

三門は山門とも称されるが、正式には三解脱門の略。中心伽藍へ入る重要な門であり、三種の解脱(さとり)を求める者だけが通れる。多くは重層の仁王門とする。例年、盛大に厳修されるお会式の、お逮夜(10月12日夜)の万灯行列が支障なくくぐれるよう、通常より下層の桁と梁の高さを上げてある。扁額「長栄山」は第80世金子日威聖人の揮毫になる。ちなみに「栄」の字は旧字だが、伝統的な慣習で、火伏せのため、冠りを「火」2つでなく「土」2つとしてある。
なお、旧三門は、慶長13年(1608)に徳川2代将軍秀忠公が五重塔と共に建立。桃山期の豪壮な門として旧国宝に指定されていた。『新編武蔵風土記稿』は、それ以前の門を、天文年間(1532-55)第9世日純聖人造立と伝える。旧扁額「長栄山」は本阿弥光悦筆になり、関東三額の一つであった。ちなみに秀忠公は、大客殿の正面にあった六足門も建立寄進している(共に戦災で焼失)。また、旧仁王尊だが、宗論による古川薬師(大田区安養寺)からの勝利尊像で、上田一族の寄進になり、和銅3年(710)行基菩薩作と伝える古像であったという。
仁王門をくぐり大堂に進みました。
2. 大堂

旧大堂は、昭和20年4月15日の空襲で焼けてしまい、戦後は仮堂でしのいでいたが、第79世伊藤日定聖人が精力的に各地を行脚し、全国の檀信徒ならびに関係寺院等からの浄財寄進を得て、昭和39年、ようやく鉄筋コンクリート造の大堂の再建にこぎつけた。聖人は落慶後ほどなくして遷化されたため、大扁額「大堂」は第80世金子日威聖人の揮毫になる。内陣中央の大型御宮殿(建築厨子)に日蓮聖人の御尊像、いわゆる祖師像を奉安し、向かって左に第2世日朗聖人像を、右に第3世日輪聖人像を安置する。また、外陣の天井画を大田区在住の川端龍子画伯に委嘱。画伯は、その龍図の完成をみることなく逝去されたが、奥村土牛画伯の指導の下に金子日威聖人が眼を点じて開眼供養をとげた。未完ゆえ龍と判別しがたいが、画伯の遺作として、今も多くの人が訪れる。
なお、旧大堂だが、第14世日詔聖人代の慶長11年(1606)、熱心な法華信者として有名な加藤清正公が、慈母の七回忌追善供養のために建立、間口25間の堂々たる大建築であった。清正公が兜をかぶったまま縁の下を通ることができたと伝える。その壮観さを江戸の人々は「池上の大堂」と称し、これに対して、上野(寛永寺)は中堂、芝(増上寺)は小堂と呼んだという。
旧扁額「祖師堂」は本阿弥光悦筆であった。同堂は、惜しくも宝永7年(1710)に焼失、24世日等聖人代の享保8年(1723)、徳川8代将軍吉宗公の用材寄進で、当時の倹約令に従い間口13間に縮小されて再建された。ちなみに同公は、大岡越前守を普請奉行に、釈迦堂・大客殿・大書院なども建立寄進している。旧祖師堂以下、すべて戦災で焼失した。
大堂の横を経蔵を横目で見ながら北に進むと本殿が現れました。
3. 本殿

昭和20年4月15日の空襲で灰燼に帰した釈迦堂を再建したのが本殿であり、場所は、旧祖師堂の左隣から境内の奥の方へ移した。開堂供養大導師は第80世金子日威聖人。昭和44年完成。現代的な鉄筋コンクリート造の仏堂建築として評価が高く、その後、各地で当堂を模す例が増えている。正面内陣には、久遠の本師釈迦牟尼仏坐像と、本化地涌の四大菩薩立像、ならびに大堂尊像を模刻した祖師像をまつる。仏教美術協会(日本を代表する仏像制作グループ)の諸師が彫刻したもので、いずれも現代の仏像を代表する作品である。ちなみに、釈迦仏の胎内には、インドのガンジー伝来で故ネール首相より寄贈された釈尊の真舎利2粒が奉安されている。
なお、古くからの釈迦堂は幾度となく罹災、天正年間の再建堂も宝永7年(1710)に焼失、第25世日 聖人代の享保15年(1730)、徳川8代将軍吉宗公が御母深徳院殿の追福のために再建した。旧扁額「釈王殿」は伏見宮親王宸筆であった。また、旧一尊四士四天の尊像は、伝運慶作、日蓮聖人御開眼であったという。
本殿から大堂の方に戻り、東に進みますと五重塔が現れました。
4. 五重塔

江戸幕府2代将軍徳川秀忠公の武運長久・病気平癒を当山に祈願した秀忠公の乳母岡部局(大姥局、法号は正心院日幸)が願主となり、秀忠公が建立・寄進した建物で、慶長12年(1607)に上棟、翌13年4月に落慶供養を修している。関東に現存する最古の五重塔である。
本塔の普請奉行は後に幕府老中を勤めた青山伯耆守忠俊、作事棟梁は秀忠公の作事を数多く手がけた幕府御大工鈴木近江守長次である。当初、大堂の右手前、現在の鐘楼堂と対の位置に建てられたが、元禄15年(1701)から翌年にかけての大修理の際に現在地へ移築された。
平成9~13年、日蓮聖人立教開宗七百五十年慶讃記念事業の一つとして、解体修理が施された。中近世過渡期の五重塔として貴重な特徴を有しており、国の重要文化財に指定されている。なお、五重塔は毎年4月第1土日に行われる五重塔特別祈願において開扉される。
五重塔の北側に力道山のお墓がありますので、ちょっと見学しました。

五重塔の奥に進みますと本門寺公園へ行く道が現れましたのでそこを進みました。
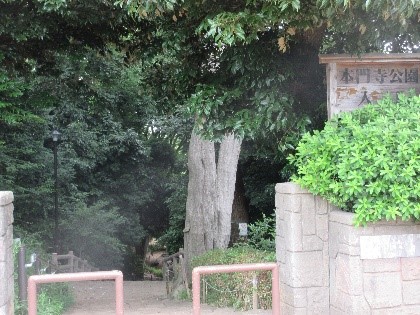
5. 本門寺公園

日蓮宗総本山である池上本門寺の境内と一体化する形で設置された公園。子供広場や弁天池、デイキャンプ場、 グラウンドがあります。森の中にあるので緑が多く散策も楽しめます。また、春になると桜が美しく咲き華やかです。子供広場には砂場やブランコ、すべり台、ジャングルジムなどの遊具があり、たくさんの子どもたちで賑わいます。弁天池では釣りも可能。グラウンドにてサッカーや野球などの球技もでき、たっぷり遊べます。デイキャンプ場は、有料・事前予約制。水場や、テーブル、レンガ作りのかまどが用意されています。弁天池の周りで休憩を取りました。
ここから貴船坂を上がり、貴船坂上で左折ししばらく歩きますと左側に池上梅園が現れました。
6. 池上梅園


池上梅園は丘陵傾斜を利用した庭園で、園内には30種、紅白約370本の梅が植えられています。区の花であるウメが約370本あり、初春には芳香を放ちながら紅白の花が咲き乱れます。また、ツツジ約800株をはじめとする樹木や、茶室、和室の施設、水琴窟があります。平成25年2月に見晴台へつながるデッキが新たに設置され、より梅の花を楽しんでいただきやすくなりました。ここで各自見学をして楽しんで頂きました。
池上梅園を出て前の道を左に進みますと先ほど池上本門寺に向かった道にぶつかります。そこを池上駅に向かって歩きました。4km弱、7000歩といったコースでした。
次回は241回「高井戸から神田川沿い・玉川上水暗渠上の緑地・寺町を巡る」です。日 時:2025年3月27日(木)10:00
集合場所:京王井の頭線高井戸駅改札口
神田川沿いに大きな公園や緑地が広がる地域です。豊かなみどりととともに古代からの歴史も探してみましょう。高井戸駅→神田川沿い(両側に桜をはじめ大きな木が生い茂り、川には大きな鯉が泳いでいます)→塚山公園(塚山遺跡を復元した住居や複製した縄文土器・石器の展示、トイレ有り)→宗源寺→覚蔵寺→玉川上水暗渠上の公園緑地→永福の寺町(8ヶ寺が集中)→築地本願寺和田堀廟所(佐藤栄作、樋口一葉の墓所)→明大前駅
5.3km、8000歩のコースです。
記事
川俣裕章

